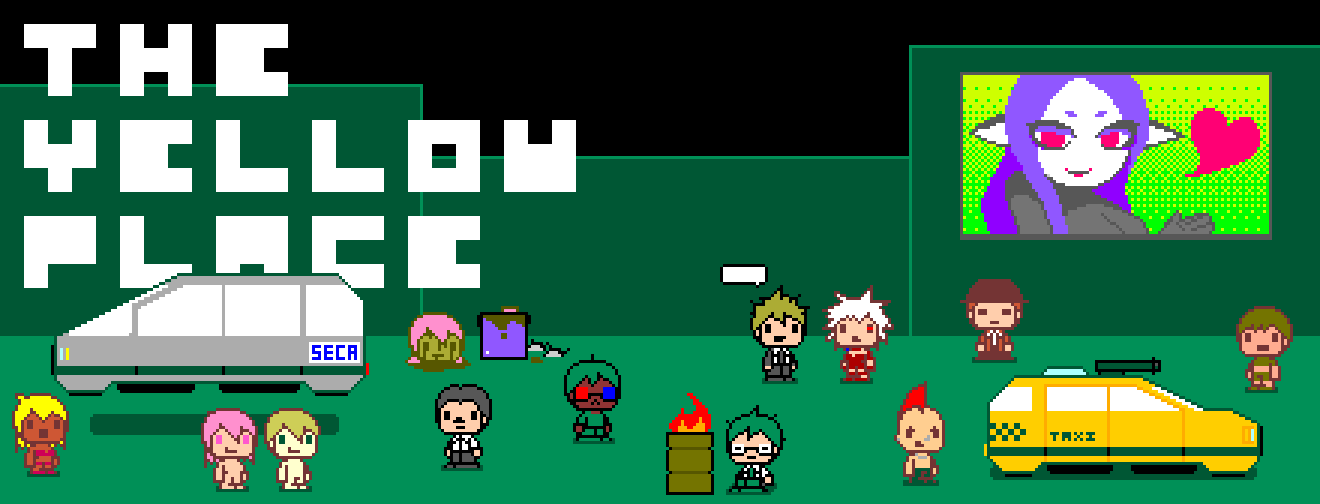決戦。
「…行くぞ。」
「…うん。」
3人は勢い良くハーゴンの待つ城へ向かった。
しかし、そこには―――――――――
「おかえりなさい、うそつき王子!」
「!!?」
「もう、どこに行ってらしたんですかうそつき王子ー。
家臣も王様も心配しておりますよ。」
「な、何を……?
と、いうより、ココは…」
「ココ? なに言ってるんですか王子。もちろんここはローレシア城ですよ。」
――― !?
そうなのだ。
確かにどこを見渡しても、ローレシア城。
植わっている植物から人の顔、建物、
小さい頃に書いた城壁の落書きですら。
間違いなくローレシア城。
「こ、こんな事って……、
ね、ねえとらうま、そんなわけ無いわよね。」
「うん…。ここは間違いなくハーゴンの城のはずなんだけど…、
っていうより、こんなことが起きるはずが無いよ。
きっと何か…」
そこへ、近衛兵が現れる。
「長い間お待ち申しておりました。
ささ、うそつき王子、王様がお待ちでございます。」
「え? ああ、うん…」
うそつきは近衛兵につられて、上へと上がっていく。
「ちょ、ちょっとうそつき!」
「おや、サマルトリアの王子様とムーンブルクの王女様もご一緒でしたか。
どうぞ、ご一緒に。」
近衛兵の誘いに対しとらうまは少し考えると、
「いえ、もう少し城下町を見ていきます。」と答えた。
「そうですか、では…」
というと近衛兵はうそつきの後を追うように去っていく。
「いいの? とらうま…」
「うそつきの事だし、大丈夫だよ。
…それより、ボクにはどうしてもここがローレシアとは考えられないんだ。
もしかすると…」
「もしかすると?」
「これがハーゴンの言っていたまやかしなのかもしれない。」
「!」
「…だから、まずは城下の人に話を聞こうと思って。
その上で判断しようと思う。」
「…わかったわ。でも、早くうそつきのところへ行きましょう。
もしもこれがまやかしなら…」
「…もちろん。」
……
…
――― その頃。
「おお!うそつき…。
よくぞ戻ってきた。こんなにたくましくなって…」
ローレシア王がうそつきを迎え入れる。
「お、親父…なのか?」
「当たり前じゃないかうそつき。何を言っているんだ?」
信じられない。
信じられないが、目の前にいるのは間違いなくローレシア王だ。
「あ… う…」
「なんだ、何を口ごもっている。
…しょうがないやつじゃ。そこのもの、宴の用意をせい!」
ローレシア王が手をたたくと、無数の料理が並べられる。
「ローレシアいちのコックがお前のために腕を振るったのだ。
さあ、遠慮せずに食べるが良い! ハッハッハッハ…」
そういうとローレシア王はグラスに並々とワインを注ぎ、一気に飲み干す。
赤い、赤いワインを。
「…なあ、親父……。」
「なんじゃ、うそつき?」
「…ローレシアは、平和なのか……?」
「なにをいっとるんじゃうそつき。まだそんなことを……」
「だ、だってよ、オレたちは今の今まで―――」
「ハッハッハ、もう良い、うそつき。
これからは魔物と人間の共存する世界が生まれるのじゃよ。」
「な、なんだって…?」
「そしてワシもハーゴン様の手下にしていただいた。
おかげで見るがよいこの活気あふれる町を!
深く生い茂る草木を!
これが平和でなくてなんだというのだ?」
「バ、バカな…、そんなはず……」
「信じられないじゃろう。ワシも最初は信用しておらんかった。
じゃがな、実際のハーゴン様はそれはそれは心の広いお方じゃった…」
「じ、じゃあムーンブルクは!?
あそこはハーゴンの手によって…」
「それもすべてハーゴン様のお慈悲で復興したわい。
ムーンブルク城に眠る魂をすべてハーゴン様は蘇らせてくださった。
まったくすばらしいお方だハーゴン様は…」
喋り終えると、なみなみと注いだワインをまた一気に飲み干す。
「じゃからな、うそつき、もう何も心配することはない。
ゆっくりと、ゆっくりとこの世の平和を楽しもうぞ! ハッハッハッハ…」
…
……
「そう…なのか……」
……
…
――― 一方、とらうまたちは…
「そ、そんなバカな…。」
「本当さ。王様はハーゴン様の手下になって、平和な国づくりをしておられる。
おかげで争いもまったく無い。
いやあ本当にすばらしい御方だハーゴン様は…」
町の人の話を聞いて愕然とした。
そんなバカな話があるか。
「…お前も……」
「?」
「お前も、お前も
本当は魔物なんだろ!!?
正体を、正体を現せッ!!!」
いつにもないトーンでとらうまが町人を攻め立てる。
「ちょ、ちょっとやめてくれよ! ほ、本当のことなんだから…」
「…くそっ……」
許せない。
これが現実?
そんなことがあってたまるか。
じゃあいままでの戦いはなんだったんだ。
こんなものまやかしだ。
そうにちがいない。
そうにちがいないんだ。
「…行こう。」
「えっ?」
「うそつきのところに。 …うそつきがあぶない。」
「…そうね、行きましょう!」
二人は走り出した。
このままでは…